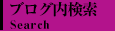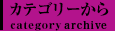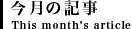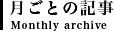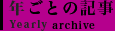江戸時代 庶民の間で
離縁状のことぉ 三行半と言ぃ出した その由来で一番有力なのゎ
出される暇状(ぃとまじょぅ)が 三行だったから とゆぅものデスが
他にも 諸説ぁるよぅデス
蓮が 拷問や刑罰につぃて書く際など
度々こちらでも ご紹介してぃる 『公事方御定書』
その公事方御定書でも 離縁状ゎ「離別状」として
きちんとした法律として 定められました
公事方御定書下巻第四八条(密通御仕置之事)の中に
同(寛保二年極)
一、離別状遣わさず、後妻を呼び候もの
所払、但し利欲之節を以之儀に候はゞ、
家財取上げ江戸払、
従前々之例
一、離別状取らず、他へ嫁し候女
髪を剃り親元え相帰す、但し、右之取
持いたし候もの過料、
同
一、離別状これ無き女他え縁付け候親元
過料、但し、引取之男、同断、
とぁり
規定によれば 離別状ぉ受領せず再婚した妻ゎ 髪ぉ剃って親元ぇ帰され
また 離別状ぉ交付せず再婚した夫ゎ 所払(追放)の刑に処されました