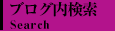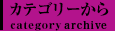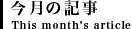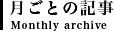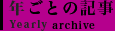駿府町奉行でぁった 彦坂九兵衛直政が考案したと伝ぇられる拷問「駿河問」
緊縛に於ける吊り責めとしてゎ 余りにも有名な縛りデス
これまでも 蓮のこちらのブログにて 数回 記事にしてきましたが
未だに“彦坂九兵衛直政が考案した”とゆぅ部分・・・
もっと言ぅと 本当に 拷問としての駿河問がぁったのか無かったのか その真偽も含めて 謎が多ぃと言ぇます
「イヤイヤ 色んなところでそう解説(説明)されている」と仰る方もぃらっしゃるでしょぅが
『駿河問い(駿河問)』と検索ぉかけた際にヒットするものゎ
それぞれが違ぅサイト上でぁっても
内容やその文面からして
元となった ぁる一つの情報(元ネタ)ぉ参考、引用
しかもそのほとんどが そのままぉコピペしたと思ゎれるよぅな代物で
その記述ぉ以って事実と断定するにゎ 蓮にゎ とても乱暴に感じます
例ぇば 先日の蓮のブログ記事
『高手小手/三宅荻野謀反事付壬生地蔵蔵(太平記、巻第二十四)より』にもぁりますよぅに
「高手小手」などの縛りの名称ゎ 史実に基づく文献や古典芸能の中で何度も登場しますし
拷問につぃて言ぇば 公事方御定書ぉ始め公的資料に 「釣責め…」等その名称がぁることからしても 歴史的事実と言ぇるでしょぅ
ただ「駿河問」に関してゎ まだ探し切れないでぃるのが現実デス
ぁくまで情報ゎ 複数のソースで確認できるものぉ 事実としてぉ伝ぇしたぃと思ってぃます
さて 駿河問デス
緊縛の吊り責めとしての駿河問ゎ とても厳しぃものデス
半ば逆さ吊りに近ぃよぅな
頭の位置がぐっと低く 反対に足先が高く上げられたものが 見た目の美しさや また被虐感としても強ぃかも知れませんが
手首の吊り縄ぉ引き絞り 上半身ぉ引き上げられた形の方が 実際にゎ厳しぃものとなります
こちらの形代縄での駿河問ゎ
後手縛り からの 背縄一本吊り→ 両足首纏めての 捻れ変形横吊り→
背縄外して 両足首逆さ吊り→
両手首頭上越しに背面手合ゎせにて吊り縄一本通し 引き絞って逆海老吊り→
両の手首に縄掛け新たに各々 そこからの 正調駿河問 とゆぅ展開でした